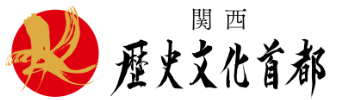-


- 関西・歴史文化首都フォーラム和歌山
-
The Road:Spiritual Journey of JAPAN
"道"は日本のこころ
- 2024年9月14日(土)
- 13:00~16:00
- 開催場所:
- 和歌山城ホール 小ホール
- 参加無料

“道”、そこを歩く人は何を想って歩くのだろうか、旅人の心を運んでいくのが“道”といえないだろうか。
心に希望や夢、願いを持って人が歩いていく、そして、そこに“道”はできていく。
紀伊半島(和歌山)が出来てきた長い歴史に想いを馳せ、巡礼を可能にしてきた“道”に焦点を当てながら、世界遺産となった地域の長い歴史やそれに伴って育まれてきた芳醇な文化を心にとどめて、今後のこの地域の、豊かな未来を想像し、創造していく思索の“道”を今日、ご一緒に歩きましょう。
申込終了
動画アーカイブ:「関⻄・歴史文化首都フォーラム」和歌山イベント
「関西・歴史文化首都フォーラム」in Wakayama
“道”、そこを歩く人は何を想って歩くのだろうか、その心を運んでいくのが“道”。
心に希望や夢、願いを持って人が歩いていく、そこに“道”はできていく。
“道”は心、そのものと言えるのではないか。遥か、いにしえの頃、古道は人々の何を担っていたのか、そして歩く人々の心は?
今年は高野山や大峯山なども含めた「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産に登録されて20年となる。平安時代から鎌倉時代にかけ、数多くの皇族や文人、そして庶民が、それぞれの想いを胸に全国各地から古道を歩いて“熊野詣”を試みた。修行として、非常に険しい道が選ばれもしたが、時代が下がるにつれ、安全な道が好まれたり、景色の良いところも選ばれるようになったという。道も生き物と言えるかもしれない。
紀伊半島の西側に位置する和歌山県。森や川や海が豊富なこの地域が、如何に信仰の地、霊性の大地と呼ばれるようになったのか。高野山、熊野、こういったところに神社仏閣の集積がなされて来、巡礼の旅が何度も何度も行われてくるようななったのはなぜなのか。
また、それとともに、体を癒す多くの温泉や、豊富で多岐にわたる日本を代表する食や食材(マグロ、アユ、鰹節、梅、醤油、柑橘類・・)が十分に和歌山には用意されている。旅人の古道歩き、そして心に潤いを与えていたはずである。
和歌山の高野山・熊野は神社仏閣だけではなく、道を含めた空間そのものが、山、川、海を含めて世界遺産である。巡礼に行く“道”そのものが信仰対象ともいえる。
紀伊半島(和歌山)が出来てきた長い歴史に想いを馳せ、巡礼を可能にしてきた“道”に焦点を当てながら、世界遺産となった地域の長い歴史やそれに伴って育まれてきた芳醇な文化を心にとどめて、今後のこの地域の、豊かな未来を想像し、創造していく思索の“道”を今日、ご一緒に歩きましょう。
【第一部】
紀伊半島=霊性の大地への“道”
今から1500万年前、アジア大陸から分離して太平洋へと迫り出した日本列島。そのウォーターフロントで起きた激烈な火山活動が、地下に超巨大マグマ岩体を形成した。この岩体がプレート運動によって押し上げられ、紀伊半島と常世へと繋がる隠国熊野の山々を作った。そして奈良時代以降、この神奈備を舞台にした神仏習合が霊場と参詣道を生み出した。世界遺産の起源を、大地と人間の営みから探る。
【第二部】
巡礼の“道”(川の“道”)
巡礼にはいろいろなルートがあった。山間部の道をめぐっていくのが多いが、かつては、海や川も活用した。ここではこれまであまり取り上げられてこなかった川の“道”を取り上げることとした。紀の川、熊野川、和歌山において非常に大きく重要な河川である。これらも、非常に古くから巡礼にも使われ独自の歴史を保ってきた。川の“道”を活用した人々の想いを感じ、和歌山の奥深さを感じていただきたい。
【第三部】
霊性の大地の未来への“道”
万博まであと半年。和歌山県も関西パビリオンにブースを持つ。そこでは、和歌山の重厚な歴史文化を如何に訴求していくのか。これからの和歌山、そして日本の未来に向けて、何を大事にし、如何に進んでいくべきかの提案がされるはず。ここでは、学生による神前神楽舞もご披露する。若者が伝統文化を懸命に取得し、その心をつないでいこうとしている。未来への希望、夢、願いを“心”に込めて、新しい“道”を探り、作っていく。